幸せを感じることは、人生の目的の一つと言えるでしょう。
しかし、幸せを感じることができない人も多いのが現実です。なぜでしょうか?
それは、自分の思考のクセが幸せを逃すNGな行動パターンになっているからかもしれません。
この記事では、幸せを逃すNGな行動パターンとは何か、そしてそれを改善する方法について紹介します。
自分の思考のクセを見直して、幸せになるための第一歩を踏み出しましょう。
他人と自分を比べる

他人と自分を比べることは、自分の価値を低く見る原因になります。
他人の成功や幸せを見て、自分は劣っていると感じたり、羨ましく思ったりすると、自分の自信や満足感が失われてしまいます。
また、他人の欠点や失敗を見て、自分は優れていると高慢になったり、嘲笑ったりすると、自分の人間性や人間関係が損なわれてしまいます。
自分と他人は違う個性や環境を持っているので、比べることは不公平で無意味です。自分の長所や短所を客観的に認め、自分らしく生きることが大切です。
過去や未来に囚われる

過去や未来に囚われることは、自分の現在を見失う原因になります。
過去の失敗や後悔に引きずられたり、未来の不安や期待に振り回されたりすると、自分の今の感情や状況に目を向けることができません。
過去や未来は変えることができないので、それに執着することは自分を苦しめるだけです。
過去や未来から学ぶことはありますが、それは現在の自分を成長させるための手段であって、目的ではありません。
自分の今を大切にし、今できることに集中することが大切です。
自分を否定する

自分を否定することは、自分の幸せを奪う原因になります。
自分の能力や容姿や性格などに対して、自分はダメだと思ったり、自分は好きではないと思ったりすると、自分の存在に対する愛情や尊敬が失われてしまいます。
自分を否定することは、自分を変えようとすることではありません。
自分を変えようとすることは、自分を肯定することの一つの方法です。
自分を否定することは、自分を受け入れようとしないことです。自分を受け入れることは、自分の幸せの第一歩です。
ネガティブに物事を捉える

物事の悪い面ばかりに目を向けると、自分の気分や行動にも悪影響を及ぼします。
ネガティブな考え方は、自分の可能性やチャンスを狭めてしまうので、ポジティブな視点を持つように心がけましょう。
素の自分を隠し、「いい人キャラ」で過ごす
自分の本当の気持ちや意見を言わないで、周りに合わせることで自分を犠牲にしてしまうと、自分の存在意義や自己肯定感が低下します。
自分を偽ることは、自分を否定することにもつながるので、自分の本音を素直に表現することが大切です。
我を通し過ぎて、周りに合わせない

自分の意見や考え方が絶対正しいと思い込んで、他人の意見や感情を無視すると、人間関係に亀裂が入ります。
自分の主張を押し付けることは、自分の孤立を招くことにもなるので、他人の立場や視点を尊重することが大切です。
自分の考え方の癖を認識する方法
考え方の癖とは、自分が物事を捉える際に無意識に使っている思考のパターンのことです。
考え方の癖は、自分の感情や行動に影響を与えるので、自分の癖を知ることは、自分の心と体の健康にとって重要です。
自分の感情や反応に気づく
自分がストレスや不安、怒り、悲しみなどのネガティブな感情を感じたり、身体的な不調や行動の変化を起こしたりするときには、自分の考え方の癖が働いている可能性があります。
そのようなときには、自分の感情や反応に気づき、その原因となった出来事や状況を思い出してみましょう。
自分の考え方を分析する
自分の感情や反応の原因となった出来事や状況に対して、自分はどのように考えていたのかを分析してみましょう。
自分の考え方には、事実に基づいたものと、自分の主観や思い込みに基づいたものが混在していることが多いです。自分の考え方には、以下のような考え方の癖があるかもしれません。
物事を良いか悪いか、成功か失敗か、0か100かなどの極端な二項対立で判断する考え方の癖です。
この考え方の癖は、自分や他人に対して厳しすぎる基準を設定し、自己評価や人間関係に悪影響を及ぼします。
白黒思考の改善方法
| 白黒思考 | 「Better」な考え | 不利益 | 利益 | 数字で可視化 |
|---|---|---|---|---|
| 仕事は完璧にこなさないと気が済まない | 仕事は完璧にこなそうとするのではなく、できるだけ良くこなそうとする | ストレスが高まる、ミスを恐れる、自分や他人に厳しくなる | ストレスが減る、ミスを許容する、自分や他人に優しくなる | 不利益:70% 利益:30% |
| 一度友人から遊びの誘いがなかっただけで、ひどく落ち込んでしまう | 一度友人から遊びの誘いがなかっただけで、友人との関係が悪くなったとは限らない | 不安や孤独を感じる、友人に依存する、自分の価値を低く見る | 安心や自立を感じる、友人に対して余裕を持つ、自分の価値を高く見る | 不利益:80% 利益:20% |
| 自分が思っているタイミングで返信が無いと、相手を非難してしまう | 自分が思っているタイミングで返信が無いことには、様々な理由があるかもしれない | 相手との関係が悪化する、自分が不機嫌になる、相手にプレッシャーをかける | 相手との関係が良好になる、自分が穏やかになる、相手に気遣いを見せる | 不利益:90% 利益:10% |
一度の失敗や否定的な経験から、自分や他人、物事に対して一般的な決めつけをする考え方の癖です。
この考え方の癖は、自分の可能性やチャンスを狭め、悲観的な見方を強化します。
過度の一般化の改善方法
| 過度の一般化の例 | 改善方法 |
|---|---|
| 面接に失敗したから、絶対に職には就けないだろう | 一度の失敗を全体に当てはめない。他の面接の機会や成功事例を探す。 |
| 友人から誘われた飲み会に行けなかったとき、私は自分は友人に嫌われると思った | 友人の気持ちを勝手に決めつけない。友人に理由を伝えて、別の日に誘う。 |
| 私は自分に自信がないという考え方が、チャレンジすることや人とコミュニケーションすることを妨げている | 自分の強みや成功体験を思い出す。小さなチャレンジやコミュニケーションを試みる。 |
物事のネガティブな面にだけ注目し、ポジティブな面を無視する考え方の癖です。
この考え方の癖は、自分の気分や行動に悪影響を及ぼし、自信や満足感を失わせます。
ネガティブフィルターの改善方法
| ネガティブフィルターの例 | 改善方法 |
|---|---|
| 仕事でミスをしたから、自分は仕事ができないと思う | 一度のミスを全体に当てはめない。ミスの原因や対策を考える。 |
| 友人からの連絡がないから、自分は友人に嫌われていると思う | 友人の気持ちを勝手に決めつけない。自分から連絡を取ってみる。 |
| 恋人と別れたから、自分はもう幸せになれないと思う | 恋人との関係を全て否定しない。自分の価値や魅力を見直す。 |
| 自分の容姿にコンプレックスがあるから、自分は魅力的ではないと思う | 自分の容姿にばかりこだわらない。自分の内面や能力に目を向ける。 |
| 他人の成功を見ると、自分はダメだと思う | 他人と自分を比べない。自分の成長や目標に集中する。 |
自分や他人、物事に対して、~すべきだ、~でなければならないといった固定観念や期待を持つ考え方の癖です。
この考え方の癖は、自分や他人に対して過度なプレッシャーや責任感を感じさせ、ストレスや罪悪感を引き起こします。
べき思考の改善方法
| べき思考の例 | 改善方法 |
|---|---|
| 学校は毎日行かなければならない | 学校に行く目的やメリットを考える。体調や状況に応じて休むことも選択肢の一つとする。 |
| 仕事は完璧にやらなければならない | 仕事の優先順位や期限を設定する。完璧ではなくても良いところを見つける。 |
| 友人や家族には常に優しくしなければならない | 自分の感情やニーズを大切にする。優しくできないときは正直に伝える。 |
| 運動や勉強は毎日続けなければならない | 運動や勉強の目的や効果を考える。自分のペースややり方を見つける。 |
| 人には感謝や謝罪をしっかりと伝えなければならない | 人の気持ちや反応を想像しすぎない。感謝や謝罪の言葉だけでなく、行動や態度で示す。 |
自分に起こるすべての出来事や状況に対して、自分のせいだと責める考え方の癖です。
この考え方の癖は、自分の自尊心や自己効力感を低下させ、自分を否定します。
自己責任思考の改善方法
| 自己責任思考の例 | 改善方法 |
|---|---|
| プロジェクトが失敗したとき、自分の役割や貢献について反省する | 自分のミスを認めて改善策を考える。チームメイトや上司にフィードバックを求める。 |
| クレームが来たとき、自分の対応やサービスに問題がなかったか検証する | クレームの内容や背景を分析する。顧客のニーズや満足度を把握する。 |
| 試験に落ちたとき、自分の勉強法や努力量に問題があったと考える | 試験の難易度や出題傾向を確認する。自分の勉強の仕方や時間配分を見直す。 |
自分の考え方を修正する
自分の考え方に考え方の癖があると分かったら、その考え方を修正することで、自分の感情や反応を変えることができます。
自分の考え方を修正するには、以下のような方法があります。
自分の考え方が事実に基づいているかどうかを確認し、事実とは異なる主観や思い込みに気づくことで、考え方の癖を修正することができます。
例えば、「私はダメだ」と思ったときには、「私はダメだという事実はあるのか? どういう根拠があるのか? 」と自問自答してみましょう。
自分の考え方が一面的になっていないかを確認し、物事の良い面や悪い面、自分の感情や他人の感情などを考慮することで、考え方の癖を修正することができます。
例えば、「彼からLINEの返事が遅いことがあって不安…」と思ったときには、「彼は仕事で忙しいのかもしれない」「彼は私のことを嫌いになったわけではないかもしれない」といった他の可能性を考えてみましょう。
自分の考え方だけでなく、他人の考え方や感情にも関心を持つことで、自分の思い込みや先入観に気づくことができます。
例えば、自分を変えるきっかけの一つとして、傾聴法やファシリテーションという手法があります。
他人の話をじっくり聴くことで、自分を見つめ直すこともできます。
ファシリテーションとは?
ファシリテーションとは、グループの参加者が互いの意見を参考にできるように調整する、集団のコミュニケーション技法です。
ファシリテーションを使うことで、グループの目標達成や問題解決を支援することができます。
ファシリテーションのポイントは、以下のようなものがあります。
グループの目的やルールを明確にすることで、参加者が何のために集まっているかを共有することができます。
グループの目的やルールは、事前に決めておくか、グループで合意するか、ファシリテーターが提案するかのいずれかの方法で設定しましょう。
参加者の発言を促すことで、グループの活性化や多様性の尊重を図ることができます。
参加者の発言を促す方法は、質問を投げかけたり、意見をまとめたり、反応を示したりすることなどがあります。
参加者の発言を遮ったり、否定したり、評価したりしないようにしましょう。
グループのメンバーが誰で、どのようなスキルや経験を持っているのかを把握しましょう。
グループのメンバーの関係や役割を整理することで、グループのメンバーの責任や期待を明確にすることができます。
また、グループのメンバーの相互理解や信頼を深めることもできます。
傾聴法とは?
傾聴法とは、相手の話をしっかり聞き、相手の感情に寄り添う一対一のコミュニケーション技法です。
傾聴法を使うことで、相手に理解や共感を示すことができます。傾聴法のポイントは、以下のようなものがあります。
相手の目を見ることで、相手に興味や関心を持っていることを伝えることができます。
目をそらしたり、他のことに気を取られたりしないようにしましょう。
相手の話を遮ったり、自分の話に持っていったりしないようにしましょう。相手の話を最後まで聞いて、相手の気持ちや考えを尊重しましょう。
相手の話を要約して伝え返すことで、相手の話を理解したことを確認することができます。
相手の話をそのまま繰り返すのではなく、自分の言葉で要点をまとめて伝えましょう。
相手の感情を推測して伝えることで、相手に共感したことを示すことができます。
相手の表情や声のトーン、話の内容などから、相手がどんな感情を抱いているかを推測しましょう。
例えば、「あなたはとても悲しんでいるのですね」「あなたはとても怒っているのですね」などです。
自分の考え方の癖を認識する
考え方の癖とは、自分が物事を捉える際に無意識に使っている思考パターンのことです。
考え方の癖は、自分の感情や行動に影響を与えるので、自分の癖を知ることは、自分の心と体の健康にとって重要です。
自分がどんな感情を抱いているかを観察しましょう。
例えば、不安や怒りや悲しみなどです。
感情は、自分の考え方の結果として生まれるものなので、感情に気づくことで、自分の考え方にも気づくことができます。
自分が感じた感情に対して、自分はどんな考え方をしているかを言葉にしましょう。
例えば、「私はダメだ」「あの人は嫌いだ」「このままでは駄目になる」などです。
自分の考え方を言語化することで、自分の考え方の癖を明確にすることができます。
自分の考え方を言語化したら、それがどのような癖に当てはまるかを分類しましょう。
自分の考え方の癖に当てはまるものがあれば、それを意識して修正しましょう。
自分の考え方の癖を分類したら、それを変えるためにはどうすればよいかを考えましょう。自分の考え方の癖に合わせて、適切な方法を試してみましょう。
ポジティブな考え方の癖3選
- 物事も人付き合いも、2:1で捉える。苦手な部分が2あるとしても、許せる部分を1見つける。
- 不完全でもいい、ありのままの自分でいいと思う。全力で頑張らない”ちょうどいい加減”を見つける。
- 物事のいい面を見つける。褒められたときは素直に喜ぶ。感謝の気持ちを表現する。
自分の考え方を見つけて、より柔軟で建設的な考え方に変えることで、心がラクになるはずです。
記事のまとめ
この記事では、幸せを逃すNGな行動パターンとは何か、そしてそれを改善する方法について紹介しました。
幸せを逃すNGな行動パターンとは、自分の思考のクセが原因で、例えば、ネガティブ思考、完璧主義、自己否定、他人との比較、未来への不安などが挙げられます。
これらの行動パターンは、幸せを感じることを妨げ、ストレスや不満を増やします。
幸せになるためには、自分の思考のクセを見直して、ポジティブ思考、自分の価値の認識、他人との協力、現在への集中、目標への取り組みなどを心がけることが大切です。
自分の思考のクセを変えることは簡単ではありませんが、継続的に努力すれば、必ず成果が現れます。幸せになるための第一歩を踏み出しましょう。
記事を読んで頂きありがとうございました。
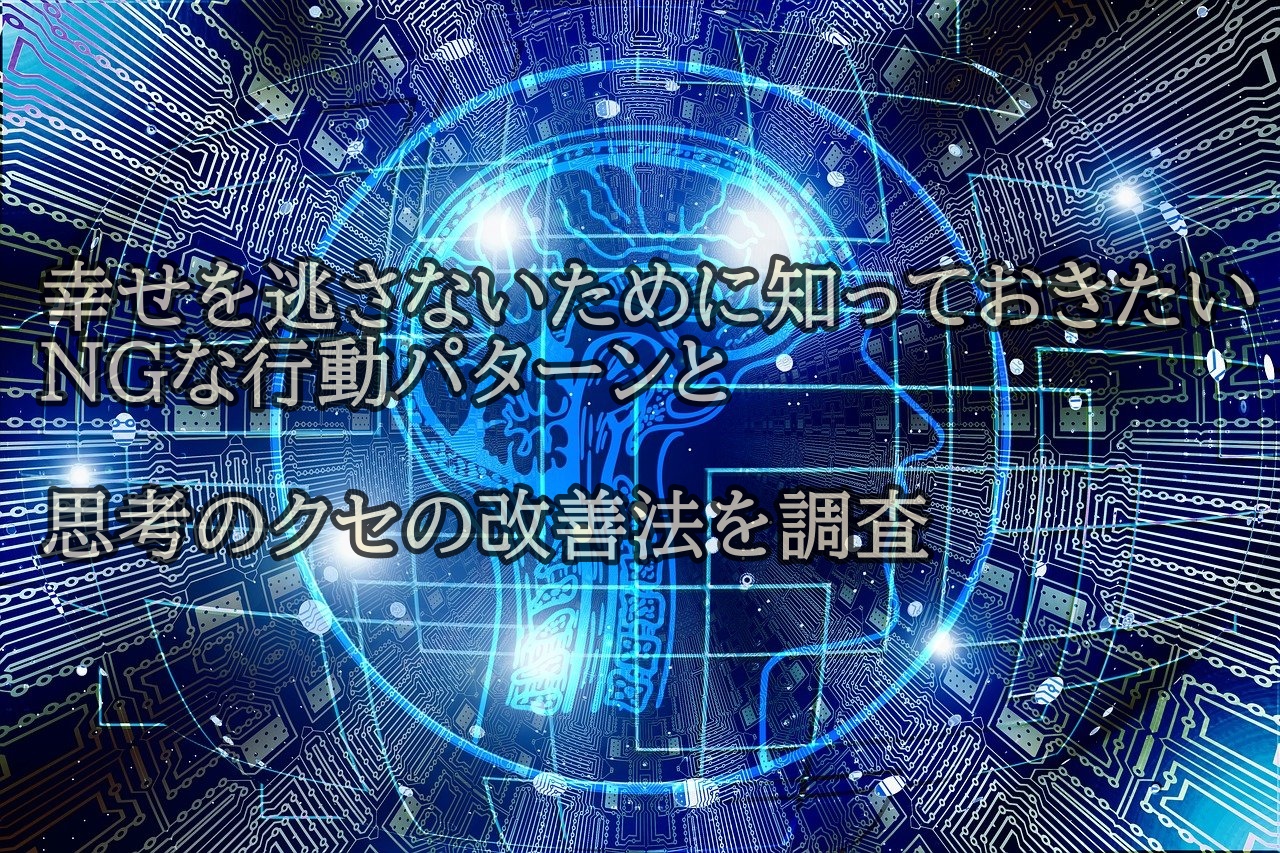
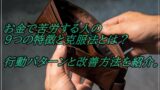


コメント